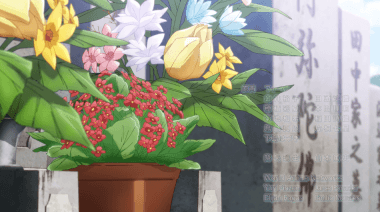昨晩、『ルックバック』を観ました。この作品が読み切り漫画としてインターネットで発表された当時、この作品を読み、どういった感情を抱いたかはもう鮮明に思い出すことは出来ません。その理由はあの漫画を読み生まれた感情のほとんどを、私自身が覚えておくことを放棄したからなのだと思います。ただなんとなく覚えているのは怒りと、悲しみと、憎しみと、感動してしまったという曖昧な記憶だけです。そんな感情たちの枝葉を思い出すことが怖かったからなのかも知れません。この映画化が発表された時には少しばかり"不快さ" を感じたことを今もよく覚えています。
だから、本当はこの映画を観に行くか凄く悩みました。それは私にとってとても覚悟のいることで、難しくて、未だ整理出来ているかも分からない出来事や感情に対して土足で踏み入られる気がしてしまって、自分が覚えておくことを放棄したはずの想いを思い出させられてしまうんじゃないかって。そう感じていたからです。でもこの作品のMVを観て少し気持ちが変わった部分もありました。登場人物たちの躍動と "心と命がそこに在る" と感じられる丁寧な芝居、表現の数々に、この作品になら託しても良いのかも知れないと思えたこと。思えてしまったこと。それはアニメーションファンとしての業に近いものなのかも知れませんが、このMVを観て「アニメが好きだ」という気持ちを反芻させられてしまったことが、私にとってはあまりにも大きかったのでしょう。
だから、繰り返しになりますが私は昨晩『ルックバック』を観ることを決めました。観て、観終えて、一晩経って今感じていることは小さな感謝と、生きていこうという些細で確かな気持ちでした。正直に言うと「ありがとう」とかそういった類の感謝とは違う感覚な気もするんですが、言葉数を知らない私が表現するならそれ以外の言葉はないんじゃないか、とも思えたので、そう書きました。それこそ、この文章を読んでくれている皆さんは「こんな気持ちになるくらいなら出会わなければよかった」と感じたことはありますか?
私は、そう "思いそうになった" ことならあります。好きなもの、愛したものを引き裂かれた時。壊された時。もう元には戻らないと気付いてしまった時。そういう気持ちに駆られそうになって、感情の行き場を見つけられなかったことがあります。でも結局、少し立ち止まって、そういう好きとか愛してるって感情をちゃんと全部失くせるのかっていうことを少し考えてみると、やっぱりそれは違うんじゃないかって強く思えてしまうんですよね。だってあなた達を好きになれたから、あの作品たちを愛していると胸を張って言えてきたから今の私が在るんだって、嫌という程に気づかされてしまうから。だからやっぱり「出会わなければよかった」なんて口が裂けても言えないし、言いたくないんです。


そしてそれは、藤野と京本にとっても同じことだったんじゃないかってどうしても思えてしまうんです。偶然とか必然とか、そういう括り方は本当にどうでも良くて、お互いが出会えたことに意味があって、出会えていなければ今はないんだっていう綺麗事の様な、これはありふれた純粋な話で。それは幸か不幸か良くも悪くもではあるけれど、与えて、与えられて生きてきた人生だからこそ、直接的であっても間接的であっても、それが人が生きていくうえで避けては通れない道であるからこそ。その半生を振り返った時にでも確かに「楽しかった」と言えてしまえるから。だから「出会わなければよかった」なんて言い切りたくないし、言えない。それは「描かなきゃよかった」と語った藤野が京本との日々を回想し、やがては机の前に戻っていくことと同じ輪郭をもって語ることが出来るものなのだと私は思います。
そして京本にとってもそれは同じことだったはず、と思いたいですよね。それこそ作品内で描かれたifの世界はもしかすれば今を生きる藤野や私たちが抱くただのエゴで、願望のようなものなのかも知れないですけど。それでも。遡ればきっと、藤野の漫画は京本の人生にきっとささやかな陽射しを当ててくれたと思うし、だからこそ彼女もまた「もっと上手くなりたい」と思えたのだろうから。そこを違うとは言いたくないですし、何かに感動して人生を動かされた経験があるからこそ、それを否定することを私はしたくありません。


それに誰かの姿を見て、背中を見て、あるいは作品を目の当たりにして生き方に影響が出るってそんなに難しい話じゃないと思いたいです。それをこの作品は何より肯定してくれているし、例えその行方に心が引き裂かれてしまう様な出来事があったとしても、そういった経験を原風景にして人はまた少しずつ歩き出し、描き綴り、日々を営んでいくことができる。この作品はそれを後押ししてくれていたと思います。そしてそれは5年前のあの日から心にわだかまりを残し続け、それでもアニメを楽しみ、彼・彼女たちの作品を待ち続けながら日々の生活を過ごして続けてきた私にとっても決して例外ではなく。エンドロールで描かれた藤野の背中と過ぎ去る風景の描写からは、そんな "生きる" ことへの罪深さと希望を携えることの正しさを同時に感じ取ることができましたし、そうして背中を軽く押して貰えたことに今は小さな感謝を感じている次第です。
以下、感じたこと箇条書き
・藤野が京本の絵に衝撃を受け描くことに没頭していく様を観ながら、人がなにかに夢中になり努力を重ねていく様はなんて美しいのだろうと思った
・京本にファンですと言われ、ステップをしながら帰る藤野の芝居が本当に良かった
・背景動画が登場人物たちの心情にとてもよくリンクしていて感動した
・泣き芝居の際だったと思うが、細かな震えや芝居として溢れ出る感情の奔流に、リズと青い鳥を感じた
・引きの絵まで何もかもが良かった
・井上俊之は天才
・押山清高は天才
・音楽が良かった
・背景の良さが京本の存在(彼女が背景画担当ということまで含め)をより際立たせていた
・サイン入りのちゃんちゃんこと4コマの原稿が対であり、対等として描かれていたのが素敵だった
・世界が広がっていく感じ、田舎の風景と部屋と都会、彼女たちが遍在する場所の全てを思い出の場所にしていく手つきに、ああ、忘れられるわけがないんだな、と感傷的になってしまった
・鑑賞後の夜道、歩きながらルックバックという言葉の意味を噛み締めていた。三好さんが手掛けてきた数々の演出回と、そのバックショットの美しさにやはり「ありがとう」を馳せながら、少しだけ泣いた
・もう大丈夫、でも少し気持ちが揺らぎそうになったらまたこの映画を観ようと、そう思えた