この作品においては通底して描かれてきた "家族観"。それは今回のエピソードでも変わらず示されており、どちらかと言えばフラットな画面で構成されたAパート、Bパートの冒頭でもそれは強く感じることができました。彼女たちを一つの画面に収める巧みなレイアウト、そこから醸しだされる雰囲気の温かさ。そういったカットが一つ一つ彼女たちの会話とともに紡がれていくのを観ていると、それだけで心が弾むような気持ちになり、「良いなあ」と強く思えてしまうのです。


しかし、ライブの日が近づくとそれまでフラットだった画面は変化し、どこか感傷的な画面・ライティングで構成されていきます。そして映し出されたのはバルコニーに佇むククの姿。揺れるカーテンの狭間で立ち尽くす彼女をアズサとライカが見つめるという構図がとても情感溢れるものになっていました。ですが、そんな遠望の視線*1をとても自然に、スッと横に立つ "隣人の視線" に変えてしまえるのが、この作品の凄みなのだろうと思います。一人で大きな舞台に立つ不安に苛まれている彼女の心を、少しだけユーモアを織り混ぜながらほぐしていく。本作においてはこれまでもずっとそうであったように、その手つきはどこまでも優しく、温かいものでした。


こういったカット、カメラワークも同様です。不安な表情のククを映しながら、スッとカメラが横に流れ背後のフラットルテが映る。そして焦点が変わる。それはまるでククのネガティブな心を横に立つ彼女が包み込むような質感すらあって、顔を上げ周りを見れば今はもう心強い仲間が彼女の傍に居ることを裏づけるような映像にすらなり得ていました。



いつもの騒がしさ。ライカとフラットルテ、アズサの声が響く中で、それを見て笑うククの後ろ姿が描かれる。そして、つい先程まで独り佇んでいたククが今度は3人を見つめる側へと回っていく。それはアズサたちがククの後ろ姿を見つめていた時と大よそ同等の関係性をもって描かれた場面でもあったのでしょう。ククに対し心を配るよう送られていた視線が、今度はアズサたちに対しての穏やかな視線として送り返され、その中で互いが互いを想う感情が寡黙に、確実に描かれていく。こういった相互関係の描写が一つ一つ着実に積み重なっていくからこそ、その果てに最後はしっかりと向き合い言葉を交わすことへの説得力が生まれるのでしょうし、そういったコミュニケーションの結実を真正面のカットで締め括った意味は、本話における "向き合う" ことの主体性を踏まえてもとても大きいものであったと言えるはずです。


また視線の置き方という点でみれば、ライブ開演前のカットはいずれも素晴らしく、前述したような夕景のシーンで描かれたことはその根幹にすら成り得ていました。ベルゼブブがやってきた後のカットなどは特にそうで、ククが現れるステージに対し大よそ対岸とも呼べる位置にアズサたちが居たことが、より "向き合う" 構造を意識させるレイアウトになっていて感傷を誘いました。それこそ背中越しに映るステージの姿は遠く、未だその全貌を見せてはいませんが*2、 "真正面に彼女たちが居る" ということをこのバックショットで描き裏づけてくれたからこそ、ククと正面から相対し続けてきたアズサたちとの関係性をより強くこのライブシーンへ重ねることが出来たのだと思います。
続け様に描かれる一人ひとりの姿は、さらに色濃くアズサたちの想いや視線の強さを訴えかける描写としても機能しており、そんな風に彼女たちの関係性とその強靭さを何度だって伝えようとしてくれるフィルムに、私はただただこの心を委ねる他ありませんでした。


そして描かれるバックステージ。不安と期待と、心細さと信じるものと。大よそ言葉だけでは表すことの出来ない感情の鬩ぎ合いを、僅かな芝居の機微とカッティングスピードで滲むよう表層化してくれる手際が強く光ります。ライブ前の焦燥感まで取り込みながら、しかしその中枢には間違いなくククの想いの強さが在ることを描き示してくれる映像の運び。前述した一人ひとりの表情を映した流れのままこのシーンに入ったこともあり、まるでその手の上にはアズサたちから受け取ったものが乗っているような質感すら感じられました。

それを裏づけるよう、ステージに立つククの目線に近いショットで描かれたこのカット。アズサたちの視線や想いの強さが幾度にわたり描かれたのなら、彼女の想いやその眼差しの強さもまた描く必要があると言わんばかりのPOV。信じた人が傍に居て、見守ってくれているというその事実だけで得られてしまう安心感。そんな感情の証左として上がる口角と、その機微を伝える繊細な表情芝居は何よりも雄弁でした。

そして、ククの眼差しの強さがここでもスポットライトのフレアとともに描かれる。それに対し、一層その瞳を見開くアズサの芝居と視線。単純な切り返しのカッティングではありますが、これがまさしく前述してきたような視線と想いを乗せたカットそのものだったからこそ、このシーンにはとても大きな意味が生まれたのだと思います。もはや会話のようにしか見えないふたりのやり取り、言うなれば「ありがとう」という歌詞の一節に乗せ送られた視線が、ダイレクトなありのままの言葉として伝わった瞬間でもあるのです。
そしてそれは紛れもなく本作が描き続け、培ってきた "家族観" の延長線上にあるものでもあったのでしょう。相手の話を聞く、視線を向ける、向き合う、想いを伝えるーー。それはとても単純なことではあるけれど、きっと彼女たちにとってはなにより大切で、だからこそそれを描くために必要とされる表現をこの作品は徹底して映像で紡ぎ続け、私たちに提示してくれるのです。


けれど、そんなアズサたちとククのやり取りも束の間に、フラットルテから観たククのステージにはまた違うものが見えていたようでした。それも、同じ吟遊詩人を愛する者としての複雑な心境というか。きっと彼女はステージで煌めくククの姿へ抱いた感動と同じくらい、スキファノイアとしては実らなかったその姿に言い知れぬ想いを抱いていたのだと思います。それはアズサの視点から見えるククのステージとはまた違う関係性の上に立つ、視点の在り方なのでしょう。
それこそ、見え方や見ている視点が違えば、その受け取り方に違いが生まれるのは当然で、いくら仲間や家族と言えど、各々が抱く感情やその風景が等しく同じものとして一致することはまずないはずです。だからこそ、それぞれを一人の人物として、その内に秘めるものを一つの感情として描いていくことが "人物を描写する" という点においてとても肝要になっていくのでしょうし、ここでフラットルテにスポットが当たったのはそういった作品の矜持をも含んでのことだったのだと思います。ククに対し、他の人たちとはまた違う寄り添い方をした存在だったからこその感情と視点。それをしっかりと提示できる物語の強み。
それこそライブシーン中盤で描かれた、多方向からのライトにより出来る幾つかの影は、そういった見え方・視点の違いや、ククが抱く想いの葛藤を暗に示していたようにも感じられて、なんだかグッと胸を絞めつけられました。


また少し話は変わりますが、そんなフラットルテの特別な感情を強く後押ししていたこのアクションカットにはとても感動しました。打ち上げ会場が盛り上がりを見せる中、フラットルテが自身の想いをククへとぶつけていくシーンですが、ここの手ブレ感が本当に良いんです。
振るわれた手の後を追うようにつけPANしていくカメラワークもさることながら、熱い言葉をなげかけるフラットルテの震える心に同期させるよう、カメラもしっかりと揺らしていくその手つき。それこそ「(スキファノイアを)絶対に永久封印なんて馬鹿げたことを考えるんじゃないぞ!」という強く激しい言葉にどれだけククが救われたのかとか。そんなことを考えると、これはフラットルテの情動に寄せた演出であると同時に、ククから見た彼女の姿でもあったんじゃないか、なんて風にも思えたりするわけです。直後にククがフラットルテを見つめるカットが差し込まれたことから考えても、このカメラブレは激励するフラットルテを見て感じたククの心の揺れとしても描かれていたのかも知れないと。

そして、さらにもう一つ。前述したものと同様、激しく叫ぶフラットルテの感情に合わせるようカメラブレがつけられたカットですが、ここの台詞。「このフラットルテだって間違って間違って間違えまくって!今、ここで生きているのだ」というその台詞の「今」という言葉からピタッとカメラブレが止まる演出が本当に素敵なんです。ここまで描かれてきたことを踏まえても、多くの感情にその身を左右されてきたであろうフラットルテですが、そんな彼女がようやく見つけることが出来た答え、居場所が一つ "ここにある" ということをカメラブレの停止で描く。それも、迷いや惑いから生じた心の揺れが今収まっているのは "アズサたちに出会えたから" なのだと、克明に示すように。
そのまま顔を上げた先にアズサたちがいるという流れでカットを繋げていたのも素晴らしく、逆に言えば視線を向ける/想いを伝える相手がいれば、その心はきっと揺らがずにすむ (カメラブレはしなくていい) ということが、このカメラワークの本懐だったのかも知れません。それこそ今思えばこのシーンで感動したことこそが、この作品に対し、視線を向けること、向き合うことへの誠実さを一番強く感じた瞬間だったようにも思います。


そして、見つめ合うふたり。横構図によってより向き合うことを強調したその意味については、もはや言葉にするまでもないのでしょう。また、このカットは奇しくもあの日ククが一人バルコニーで佇んでいた時のものとほぼ同様のポジションカットでした。一人で居たはずの場面が二人になり、二人だからこそ視線を交わすことができるという、そんな確信に至るまでの時間経過を描き切ったフィルムの温かさ。短い間ではあったけど、そんな風に濃密な時間をククは過ごせたのだと思えることこそが、今回の話においてはとても大切だったのだろうと思います。
誰かに見つめてもらえているという安らぎと、見つめることが出来るという喜び。そういった関係性の上に繋がっていく個々人の感情を、どこまでもうまく救い上げてくれた挿話だったなと思います。最後は円満の象徴である満月を背に笑顔をみせる二人。このラストシーンを観終えた後に「まるで家族のようだ」 と思えたことが、今話における最大のハイライトでした。心に残る、強く好きだと信じられるエピソードに出会えたことに感謝を。本当にありがとうございました。






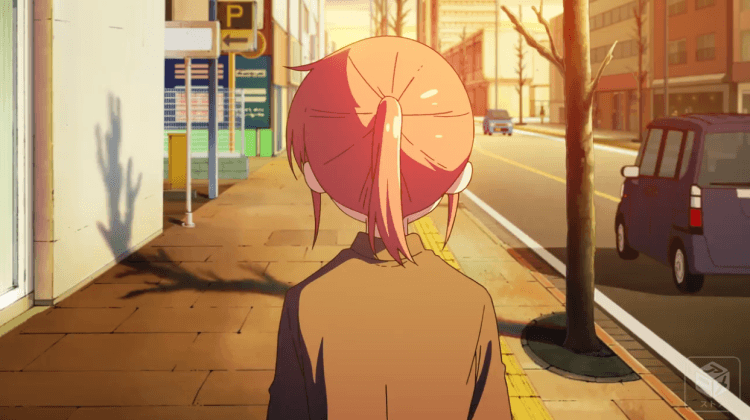







![[初回限定版Blu-ray]小林さんちのメイドラゴンS(1)(特典なし) [初回限定版Blu-ray]小林さんちのメイドラゴンS(1)(特典なし)](https://m.media-amazon.com/images/I/51aE5Z9okLS._SL500_.jpg)






