

先週、鑑賞した『サイダーのように言葉が湧き上がる』。久しく素晴らしいボーイミーツガールを観たという感慨に浸れた本作ですが、その中で何よりも先ず良いなあと唸らされたのが、独自の世界観を獲得していたシティポップテイストのある背景美術でした。ビジュアル自体が強く印象に残ることもそうですが、この背景があるからこそ一つ一つのカットが一枚のイラストとしても成立してしまうような強度を携えていて、まるで一瞬一瞬を彼女たちにとっての大切な風景として収めているような風合いさえそこには感じられました。
特に本作では "俳句" というものに一つ焦点をあてたストーリー構成になっていたわけですが、思い返せば前述したようなことは俳句そのものにも同じことが言えるのだと思います。その瞬間に目前に広がる風景、そしてそれを見て感じた自身の感情を言葉にして綴じ込める。俳句のすべてがそういった構成に当てはまるということではないのかも知れませんが、季語というものが存在するように、やはり俳句においてはある瞬間・風景を想像し得る構成というものが要になってくるのでしょう。それは主人公であるチェリーが多くの感情や目にした風景を俳句にしたためていたことからも分かると思いますし、劇中に登場した「やまざくら かくしたその葉 ぼくはすき」「夕暮れの フライングめく 夏灯」などの俳句はそうした感情と風景の代名詞として、本作を代表する表現にさえなり得ていたはずです。
そしてそういった俳句の構成が、特異的な背景美術を基盤とした本作の映像面にも強く投影できるのではというのが最初に触れたことの趣旨であり、答えなのです。まず強く目に残る背景が在り、そこに色彩、撮影、芝居作画といった多くのハイクオリティの描写が乗ることで一つ一つのカットが印象的なものになっていく。そして、そんな風に一つ一つのカットを印象的なものにするということ自体が、物語的にみれば一つ一つの瞬間を大切なものとして残しておくことにも繋がっていく。そういった流れが本作の中で積み重なっていくからこそ、ラストシーンのチェリーの回想にもより強い意味が宿っていき、より大きな感動に繋がっていったのだと思います。フジヤマが探していた奥さんのピクチャーレコードなんてまさにその象徴ですよね。奥さんとの出会い、その瞬間に生まれた感情と風景の美しさが歌声とともにあのレコードに収められている。本作にとっての絵の力強さというのは、そういった感情的な部分にまでしっかりと同期しているのです。
特に個人的に好きだなと感じたのは、二人が畦道を歩くバックショットです。異なったレイアウトにより幾度か描かれたシチュエーションではありますが、これこそまさに詩的 (俳句的) なカットだったというか。寡黙に、けれど雄弁に二人のバックボーンとその道行く先を示唆する描写。覆い茂る葉、広がる田園の風景はそんな二人の出会いを包み込むようで強く胸を打たれました。


また、もう一つとても良いなと感じた構成 (演出) がありました。それは、引っ越しのための片付けをすることと、店仕舞いのため店内を整理する/片づけることが同時進行的に描かれていたことです。
それこそ、同じ "片づける" という行動にしてもその意味はまるで違います。部屋を片づける行為は逃れられない*1運命に従うような印象がありましたが、こと店仕舞いの片づけに関しては、そもそもが "想い出のレコードを探す" ことがその目的の大半を占めていました。ようは前向きであるか、そうでないかの差がそこにはしっかりと横たわっていたということなんです。やれないことと、やりたいこと。どうすることも出来ないことと、どうにかしたいこと。そういった線引きがここではしっかりと示されていました。そして、それはスマイルに引っ越ししてしまうことをなかなか打ち明けることが出来なかったチェリーの感情に対しても、強く重ねられていたのだと思います。


でも、青春ってそういうものだとも思うのです。親の決定に逆らえない場面が往々にしてあったり、自分ひとりの力ではどうしようもないことがあったり。けれど、それでも "やりたい" という気持ちは否応なく溢れてきてしまって、その狭間で悶々としたり悩んだり、時には喜び笑い合ったりすることだってあるのです。それはまるで振られた容器の内側で弾けるサイダーのようでもあって、チェリーはそういった圧と圧の鬩ぎ合いの中で懸命に考えていたのだと思います。
でもやっぱりこれは青春だから。どうしたって溢れて、零れてしまうものだから。それはレコードから流れる歌声を聴いたフジヤマが大粒の涙を溢れさせていたこととも大よそ同じ輪郭をもって語ることの出来る感情の導線であり、結局チェリーにとってもこの物語の結末は避けようのない "感情の選択" だったのでしょう。だからこそ、"やれないこと" と "やりたいこと" の一線をまるで超えるよう遮断機を跨ぐカットが描かれたことにはかなりグッときてしまいましたし、もしかしたら終盤の分割カットでさえそんな二人の間に立ちはだかる最後の壁を越えるためのものでもあったのかも知れません。
その壁を越えんとするように描かれた、溢れ出したら止まらない言葉の投げかけは観ていて少し恥ずかしさもありましたが、きっとそういうものも全て含め、人は青春と呼ぶのでしょう。それを受け最後はスマイルの "笑顔" で終わるというのも、本当に最高でした。きっと彼女にとってはあの場面こそ "感情が溢れた" 瞬間であり、マスクを外すことそのものがチェリーの言葉に対する応えにもなっていたのだと思います。
感情や環境の狭間で揺れる少年少女たちの感情の行く末を爽やかに歌い上げた映画、『サイダーのように言葉が湧き上がる』。そのタイトルの字面通り、観終えた後にたくさんの想いや感動が湧きあがってくる作品でした。心の底から観て良かったと、強く思えています。
*1:引っ越ししなければらない






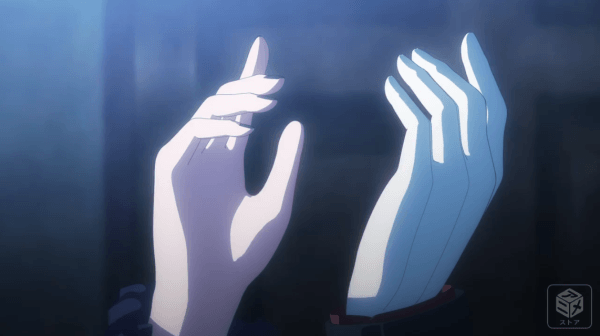








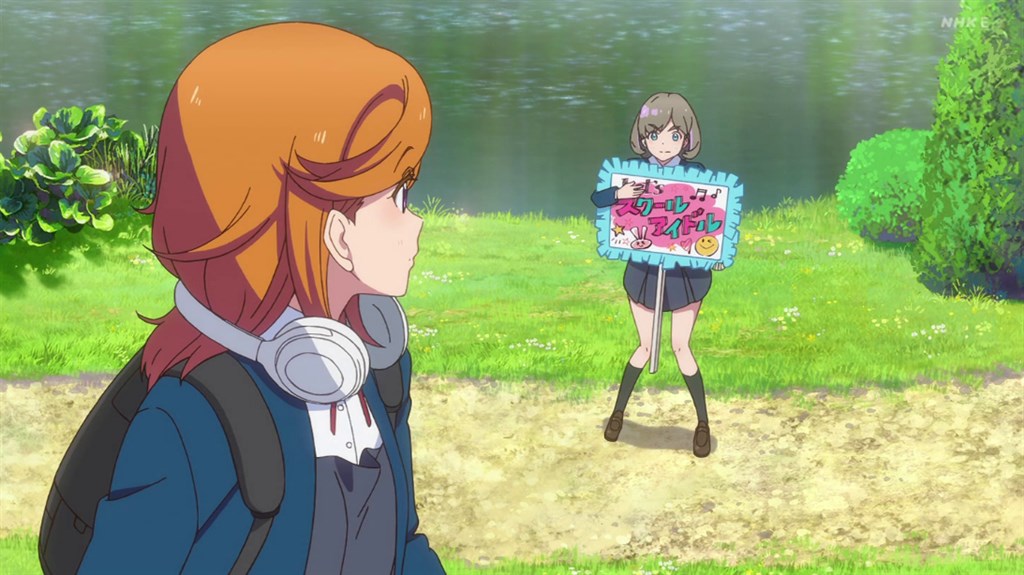












![ラブライブ! スーパースター!! 1 (特装限定版) [Blu-ray] ラブライブ! スーパースター!! 1 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ymKrymkqS._SL500_.jpg)